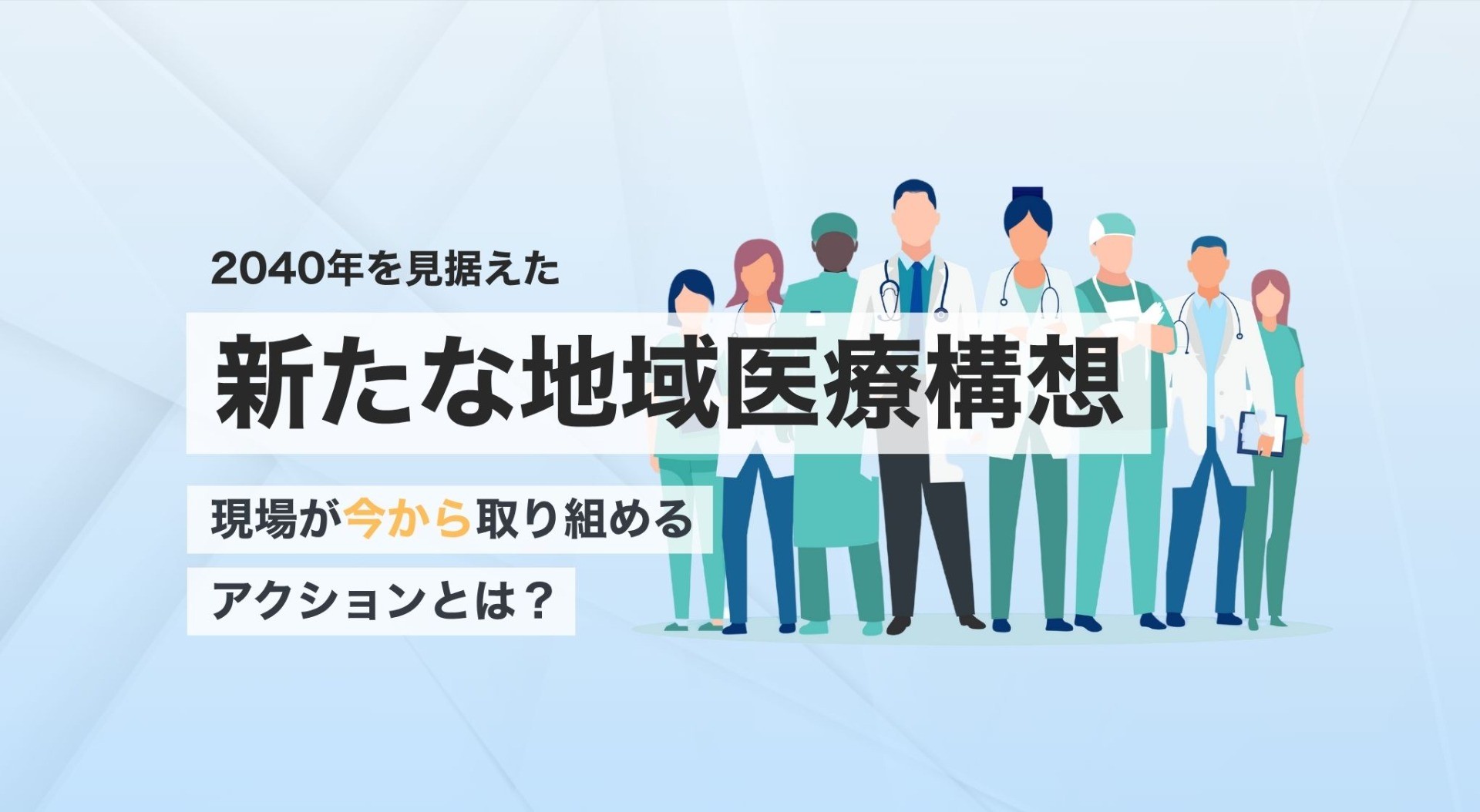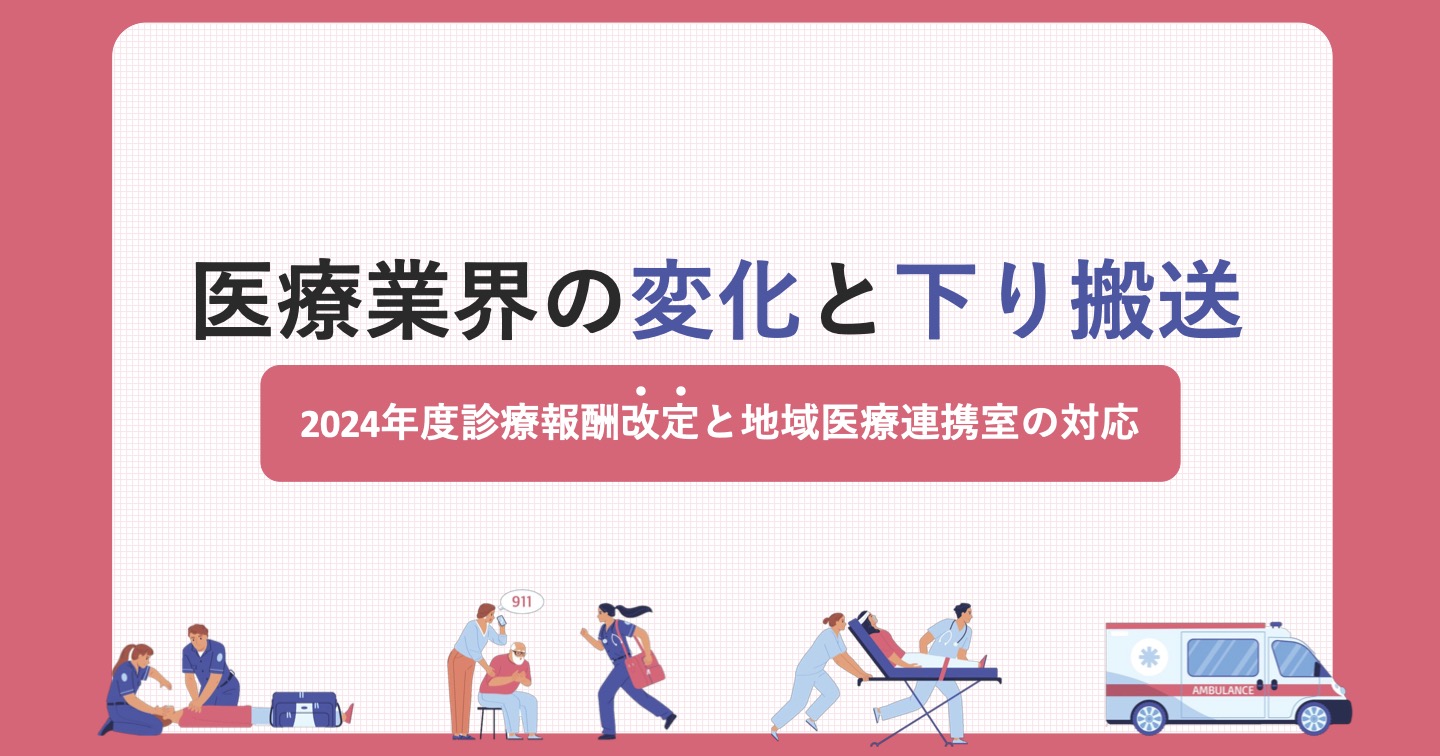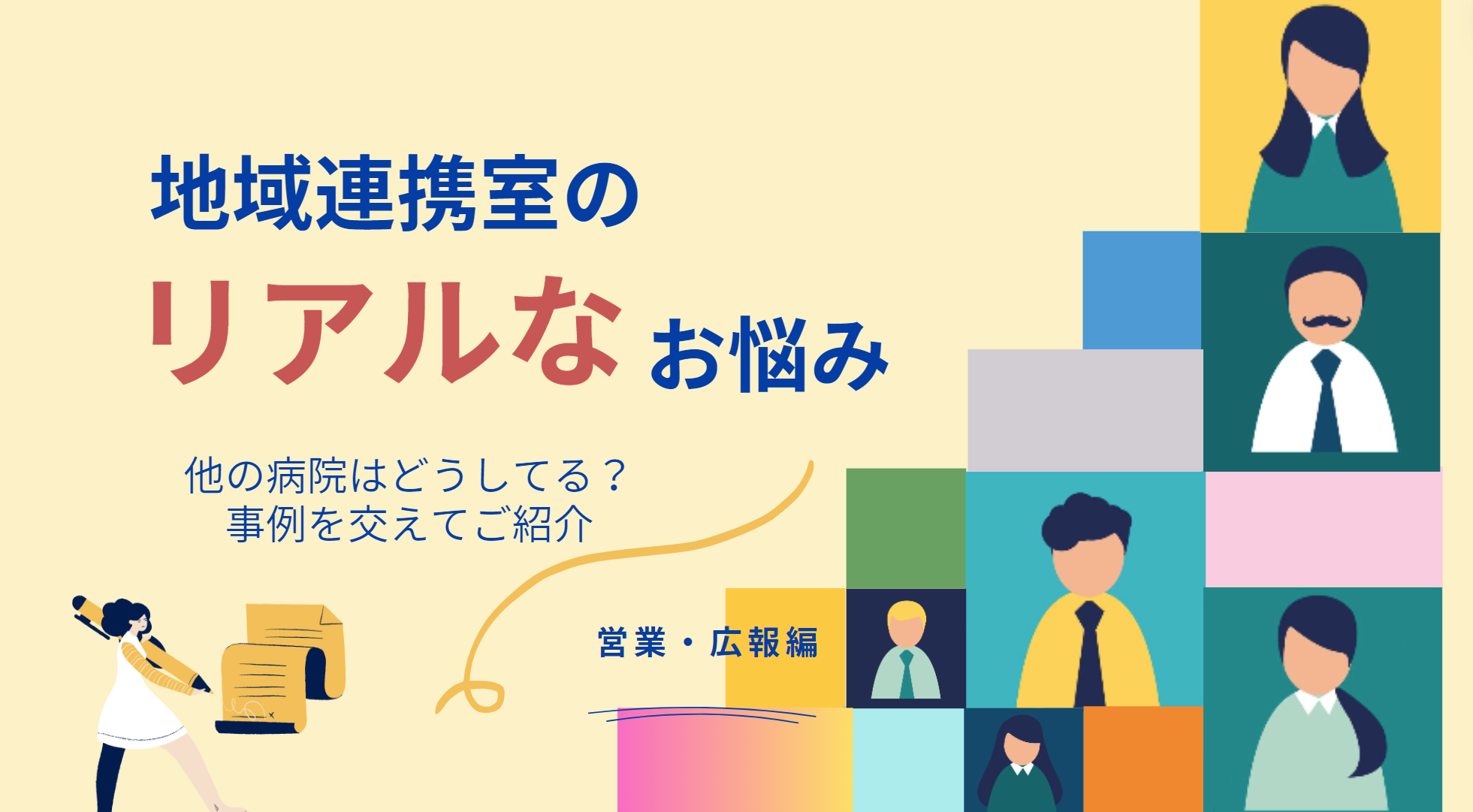medigle press
2021.03.18
Hospital Management to Win
生き残れる病院のキーワードは「選択と集中」
「データ」を活かし「強み」を知る

佐藤 敏信 氏
久留米大学特命教授、医療政策担当教授
1983年山口大学医学部卒業後、厚生省(現在の厚生労働省)入省、2014年の7月までの30年間、地方行政も含め、医療政策に携わる。2017年久留米大学特命教授就任、医療政策担当教授として教鞭を執る。
新型コロナウイルス感染拡大で医療機関への影響が長期化している。
国内の医療機関の経営状況の悪化も深刻さが増し、生き残りをかけた病院淘汰の時代が始まろうとしている。
長年、厚生労働省の医系技官として、日本の医療政策に携わってきた、久留米大学教授佐藤敏信氏に勝つための病院経営と地域医療の今後について聞いた。
収益性の高い疾病はわずか上位100
通常はもっぱら稼働額に着目し、その多寡や増減を、診療科間で時系列的に比較というところがせいぜいだろう。
久留米大学病院で、平成30年度の診療実績をx軸に稼働率、y軸に粗利を取って分析したところ、DPCの2000 項目中、病院全体の収益に大きな影響を及ぼしているのは上位100程度。
たとえば弁膜症の弁置換術、肺の悪性腫瘍、頻脈性不整脈のアブレーション、脊柱管狭窄症、白内障の手術等だった。とりわけ、アブレーションに関しては診療行為の数だけで考えると2000分の1であるにもかかわらず、年間で億単位の収益を産み出しているという。
病院を製造業に例えると、多くの病院は多品種少量生産。医療スタッフはその中で黙々と頑張っている。同じ努力をするのなら、持っているデータを分析し、先ほどのアブレーションや肺がん手術などを1.2倍ぐらいにした方が経営への影響は大きい。
個々の病院の中でも、診療科間、医師間、あるいは職種間のバランスや協調だけを重視する「護送船団方式」の日本ではそういう発想が今までなかったと佐藤氏は言う。病院内で収益が上がる診療科行為を見つけ、それらを高く評価することも、その逆も憚られる傾向にあったからだ。
では、収益をどうやって伸ばせばよいのだろうか。「もう一度アブレーションを例にとると、担当している医師は何人で、週何回実施しているのかを聞き取りました。さらに実施回数を増やすために何が必要かも。すると、処置室が不足しているということがわかりました。予備としている処置室の改装によって1部屋増やして対応できるのではないかと考えたのです」と佐藤氏は話す。
このようにまずは診療行為を細分化した上で、収益に影響の大きそうな分野を選び出し、次に、より詳細なデータ分析と現場のヒアリングとで伸ばせばいいということだ。このような手法で実行することを「選択と集中」というのだろう。
予定手術と緊急手術を見極める
佐藤氏によると、次に重要なのは「目利き」。上述のような作業を機械的にやればいいということでもないという。人口動態統計などを見ながら....
残り3,422文字
人気の記事
-
2020.09.24
-
2020.07.28
-
なぜ今、地域医療連携にCRMが必要か。顧客管理の視点で地域医療連携を考える。
2021.07.21
最新の投稿
-
2040年を見据えた新たな地域医療構想 —今から取り組めるアクションとは—
2025.06.05
-
医療業界の変化と下り搬送 2024年度診療報酬改定と地域医療連携室の対応
2024.05.15
-
2024.03.28